柵の発掘作業風景
柵とりあげまでの工程
「柵」のような遺物はこれまで国内では出土したことはありません。したがって、誰も取上げた経験はありませんでした。
しかし、出土しても遺物を放置しておくと、劣化して焼いたスルメのように丸まってしまいます。ともかく取上げることにしました。
ウレタンで包んで、重機で取上げるという選択肢もありましたが、数が多くてとても時間的に間に合いそうにありませんでした。
そこでとりあえず力業で取上げることにしました。この方法がとれたのは、「柵」が埋まっている地層が主に砂礫であったためです。


発掘1

「柵」発掘風景。遺物が乾燥しないように十分に水分を含ませてから、
ラップとタオルで保護しながら掘り進めてゆく。
発掘2

柵発掘風景。ほぼ全景が見えている。たけべらで表面だけを取除き、
あとは水力で飛ばしていく。
発掘3

ブドウつるや皮はもろくはがれやすいため、 水の勢いは最小限に抑えて、遺物に当てる。
清掃

柵の全景が確認できた段階で、周辺を清掃し、 写真撮影を行う。
その間にも常時水をまき乾燥を防ぐ。
実測
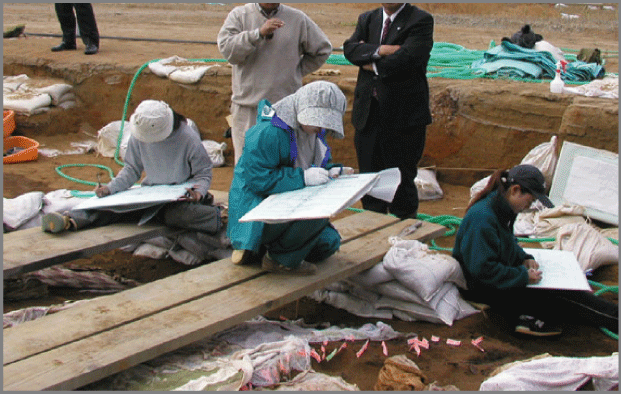
実測中も全体にぬらしたタオルをかけ、実測部分だけをあけて描く。
大きい柵には板をわたし、その上に乗って実測する。
取り上げ1

割木と割木の間を互い違いにスプーンで掘り、溝をつくっていく。
取り上げ2

等間隔に添木をおき、紐状にした不織布で添木と割木を結んでいく。
取り上げ3

さらに、割木にも添木をして不織布で結んでいく。
取り上げ4

結び終えたら、慎重に持上げ最適な大きさの箱に梱包する。
その際、箱には遺物全体を覆える大きさのビニールとぬらした不織布をひいておく。
取り上げ終了

大きな柵の場合には、持上げる時にかかる遺物への負担を考えて、
分割して取り上げを行った。写真のは2分割。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











