行事・講座案内2013年度
テーマ展 資料館のお宝2014
2013年12月21日(土曜日)から2014年3月30日(日曜日)


「資料館のお宝」展では、毎年皆様からご寄贈いただきました資料を紹介しています。
今年も石狩市内外の方から、貴重な資料を多数寄贈していただきました。
資料館のお宝はみんなのお宝――感謝の気持ちを込めて、展示させていただきます。
野外講座 石狩ビーチコーマーズ/冬の漂着物
2014年3月2日(日曜日)

冬の北西季節風は、たくさんの漂着物を浜に吹き寄せます。外国からのボトルも見つかります。
海のゴミ問題や、気候変動など、漂着物から海の世界の事件を覗いてみましょう!
※原則として、吹雪でも開催します。
連続講座 石狩大学博物学部(全2回、4科目)
2014年1月25日(土曜日)、2月1日(土曜日)
石狩って、どんなところ?
石狩の自然と歴史を調査している4人の学芸員が、最近の研究成果やトピックを写真や図を使ってわかりやすく解説します。
1科目だけの受講もOK。3単位(3科目)修得(受講)した方には、修了証を発行!
講座日程 1時間目 1月25日(土曜日)13時から14時
科目
石狩海洋学 2012年の海辺の異変
講師
志賀健司
内容
ヤシの実、大量のアオイガイ、タコブネ…。2012年の石狩の海辺では、異常といえるほど大量の暖流系漂着物が見つかりました。その背景には、いったい何が?
講座日程 2時間目 1月25日(土曜日)14時10分から15時10分
科目
石狩民俗学 石狩川の主はどこにいる?
講師
石橋孝夫
内容
石狩川の主はチョウザメだと江戸時代から伝えられていますが、主がどこにいたか、なぜ主なのかを考えてみましょう。
講座日程 3時間目 2月1日(土曜日)13時から14時
科目
石狩考古学 縄文の木の器
講師
荒山千恵
内容
遺跡に残りにくい木の道具。これまであまり知られることのなかった縄文文化の「木の器」について紹介します。
講座日程 4時間目 2月1日(土曜日)14時10分から15時10分
科目
石狩歴史学 札幌の石狩鍋
講師
工藤義衛
- 時間
- 13時00分から15時20分(2日とも)
- 場所
- 石狩市民図書館 視聴覚ホール(北海道石狩市花川北7条1丁目)
同時開催!ミニ展示 縄文時代の木の道具 木の器
2014年1月21日から2月4日

石狩市民図書館エントランス 石狩紅葉山49号遺跡から出土した「木の道具」。
遺跡から出土した「木の器」を紹介する写真パネル、復元模型等を展示。
テーマ展 縄文の木の器
2013年8月28日(水曜日)から11月11日(月曜日)


石狩紅葉山49号遺跡から出土した縄文文化のさまざまな道具。
その中から、今回の展示では、木を素材に作られた、いろいろな器(縄文時代中期、約4000年前)を紹介しています。
縄文時代の「木の器」って何だろう どんな形?大きさは?
何の木で作ったの?どうやって作ったの?何に使ったのだろう?「木の器」には不思議がいっぱい!
野外講座 石狩ビーチコーマーズ/秋の漂着物
2013年10月27(日曜日)


秋の石狩浜では、南から暖流で運ばれてくる漂着物がたくさん見つかります。それらを観察・採集し、正体や起源、漂着の原因をみんなで考えます。
体験講座 鉱物パラタクソノミスト養成講座(初級)in石狩
2013年10月19(土曜日)


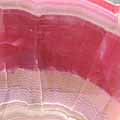


いろいろな鉱物の性質や鑑定方法を、講義とたくさんの標本を使った実習で学びます。
- 場所
- 石狩市民図書館(石狩市花川北7条1丁目)
- 講師
- 松枝大治さん(北海道大学総合博物館研究員・名誉教授)
トークイベント ウミベオロジ―/石狩海辺学2013
2013年10月6日(日曜日)






海辺は、海と陸との境界線。
境界線では、いろいろな出会いがあります。
札幌からもっとも近い海、石狩の海辺。
海と陸に、石狩川も加わります。
川から海へ。
海から川へ。
海辺の知られざる姿を、自然と文化の両面から3人の学芸員(当館2人+お客様1人)が語る!
- テーマ
-
- 川から海へ 陸からやってくる漂着物
志賀健司(いしかり砂丘の風資料館学芸員) - サケ 海から川への遡上
有賀 望(札幌市豊平川さけ科学館学芸員) - 鮫様 チョウザメの神様
石橋孝夫(いしかり砂丘の風資料館学芸員)
- 川から海へ 陸からやってくる漂着物
- 日時
- 10月6日(日曜日)16時30分から18時00分
- 場所
- 紀伊國屋書店札幌本店(札幌市中央区北5条西5丁目)1階インナーガーデン
体験講座 サケ缶レプリカをつくって、サケの歴史をみよう
2013年9月15日(日曜日)




石狩と言えば、サケ。でも、どうして?
特別バージョンのサケ缶レプリカ製作、展示や本町市街の見学から、サケと石狩の関わりを体験します。
石狩のことをまだよく知らない、「石狩初心者」にオススメの講座!
体験講座 勾玉作り
2013年9月8日(日曜日)

勾玉とは、古代の人々が魔除け、装身具等として石などで作り、身に付けていたものです。
今回は、磨き上げないと出てくる模様がわからない「モザイク」という種類の
滑石を使って勾玉を作ります。
体験講座 ミニチュア「縄文の木のうつわを作ろう」
2013年8月31日(土曜日)

石狩紅葉山49号遺跡から出土した木のうつわをもとに、
ミニチュアで木のうつわを作りながら、縄文時代の木の文化について学びます。
講師は、「WOOD LANDER'S 木那」の片岡祥光さん。
体験講座 サケ切身骨格標本をつくる
2013年8月17日(土曜日)


食卓でおなじみのサケですが、骨をじっくりと観察したことはありますか?
スーパーで売っているサケの切身から骨を取り出し、きれいに処理して学名ラベルを付ければ、立派な部分骨格標本のできあがり!
- 魚には“目の骨”がある?
- 魚と爬虫類・哺乳類の骨を見分けるには?
- 魚も人間も、骨は同じパーツでできている?
魚にも「肩甲骨」がある?
答はこの講座で!
体験講座 縄文土器復元講座
2013年6月29(土曜日)から(全3回)

縄文土器の復元にチャレンジしませんか?3回の講座で初心者でもみっちりとご指導します。
体験講座 テンキ作り ハマニンニクで小かごを編む
2013年7月27(土曜日)


石狩の海辺にみられるハマニンニクの葉を材料に、アイヌの工芸「テンキ」作りに挑戦します。
※共催:石狩浜海浜植物保護センター
※いしかり館ネットワーク事業
体験講座 化石パラタクソノミスト養成講座(初級)in石狩
2013年7月13(土曜日)

化石標本を観察し、古生物学の基礎を学びます。
現生動物の骨格や化石骨を観察、計測、。スケッチし、比較考察を行ないます。
自然観察会 石狩川下流をさかのぼるツアー
2013年7月6日(土曜日)

石狩川の下流域を貸切バスで移動、河口から豊平川合流地点までさかのぼります。
地形や植生を観察しながら、かつての風景の名残りをたどります。
石狩、小樽、札幌の博物館等の学芸員が案内・解説します!
※石狩市、札幌市、小樽市の共催。
野外講座 地層と化石
2013年6月22(土曜日)


800万年前の地層と化石を見て、触って、採集して、生命と地球の歴史を読み取ります。
野外講座 石狩ビーチコーマーズ/春の漂着物
2013年4月14(日曜日)

冬の間にたまったたくさんの漂着物は、春に雪が融けると顔を出します。それらを観察・採集し、正体や起源、漂着の原因をみんなで考えます。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











