いしかり博物誌/第36回
第36回 遠ざかる河口

明治25年(1892年)に運用が開始され、今でも石狩浜のシンボルとなっている石狩灯台(写真1)。その先には、1.5キロにわたってハマナスなどの海浜植物が生い茂る、石狩川河口地区が広がっています。でも、ふつう灯台といえば岬など陸地の先端にあるはず。なぜ石狩ではこんなところにあるのでしょうか。
北海道一の大河、石狩川は、上流から大量の土砂を河口まで運んできます。航空写真を見ると海側の水は青っぽいのに、川側は土砂で黄色く濁っているのがよくわかります(写真2)。河口地区は、このようにして運ばれてきた砂が集まってできた、幅300メートルほどの細長い陸地なのです。このような地形を砂嘴(さし)といいます。

小石や泥にくらべて、砂は水の流れでさらさらと簡単に移動してしまいます。そのため砂でできた地形はどんどん変化していきます。1978年と1995年の2枚の航空写真を見比べてみてください(写真3・4)。
わずか20年足らずのうちに、河口地区の先端部(ループ状の道路に注目)や、海側の砂浜が大きく変化しているのがわかると思います。今からほんの2から3年前までは1995年の写真のように砂浜がすっかり消えて、緑におおわれた砂丘まで波で削られていましたが、今はまた砂浜が復活しています(写真5)。
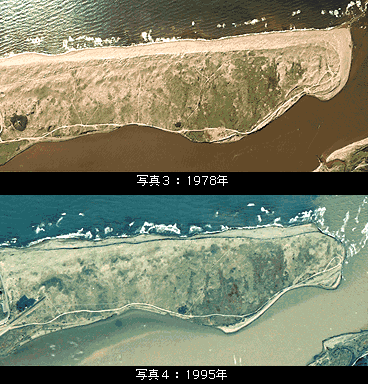
写真4:河口地区の航空写真(1995年)

江戸時代の鳥瞰図や明治時代の地形図から、河口地区の砂嘴は今よりも短かったことがわかっています(図)。
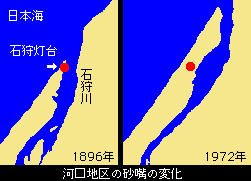
今から110年前、完成したばかりの石狩灯台は砂嘴の最先端の地にありました。しかし石狩川が運んでくる砂によって陸地が少しずつ成長し、河口は灯台からどんどん遠ざかっていったのです。
当時、新築の灯台のすぐ目の前では、石狩川が日本海に注ぎこんでいたことでしょう。 (志賀健司)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











