いしかり博物誌/第13回
第13回 ビールもつくる「珪藻土」(けいそうど)
夏です。ビールの季節です。きゅっと冷えた生ビールをぐいっ。そんな幸福にひたれるのは「珪藻土」という岩石の恩恵であることをご存じでしょうか。
珪藻土とは植物プランクトンの一種「珪藻」の死骸が集まってできた軟らかい岩石です。
珪藻は大きさ0.01から0.05ミリで、無数に穴のあいた殻をもっています。そのために珪藻土は水や空気の小さなゴミを取り除く性質があったり、軽い、断熱性が高いなどの特徴があります。ビールは麦芽とホップを酵母で発酵させて作りますが、最後に酵母を取り除くためのフィルターとして珪藻土が使われているのです。また七輪コンロの材料、最近では家の壁に使うこともあるようです。そんな珪藻土が、このシリーズにたびたび登場している市内の紅葉山49号遺跡から出土しています。
実は珪藻土は、昔から食べられる土としても知られていました。遺跡から出土したのも、当時の人、おそらく江戸時代のアイヌが食物として使っていたためでしょう。ところが遺跡の近くはおろか、石狩市周辺にも珪藻土が採れる地層はありません。では一体どこから運ばれてきたのでしょうか。その手がかりとなるのが、含まれている珪藻の種類です。
珪藻はわかっているだけでも1万5千種類以上いますが、海の珪藻、湖の珪藻、すでに絶滅したものなど、場所や時代によって見られる種類が違います。北海道には珪藻土の産地はたくさんありますが、やはり中に含まれている珪藻にはそれぞれ特徴があるのです。
ということは遺跡のものも、種類を調べればどこから採ってきたのかわかるはずです。
さっそく顕微鏡で調べたところ、今から500万年前の海でできたものであることがわかりました。残念ながら道内の産地の多くがその条件を満たしているので、1か所に特定することはできませんでしたが、おそらくは渡島半島や道北地方のような、意外と遠くから運ばれてきたらしいことは確かです。
ただの土の固まりに見えても、当時の人々の活動を知るカギになるのです。ビールだけが珪藻土の恩恵ではないようです。 (志賀健司)
※珪藻土を食べる話は、博物館開設準備室だより「エスチュアリ」第3号に詳しく書かれています。バックナンバーもありますので、ご希望の方はご連絡ください。
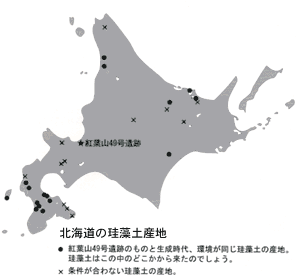
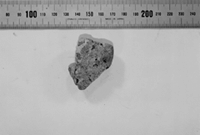
一見ただの白っぽい土のように見えますが・・・。
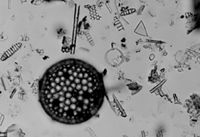
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











