いしかり博物誌/第24回
第24回 紅葉山49号遺跡の木製品
遺跡からでる遺物はふつう、土器、石器、そしてまれに骨や角で作られた骨角器(こっかくき)などが主です。しかし、当時利用されていたものは木や植物、毛皮などといったものも当然あったはずです。ところが、木や植物などはたいへん腐りやすい性質をもっていて、泥炭など水漬けのような特別な場所でなければ残りません。
昨年、サケマスの捕獲をねらって設置されたと見られる「エリ」が出土した紅葉山49号遺跡もその特別な条件の遺跡です。ここで泥炭は一部にしか見られませんが、河川跡ということで冷たく豊かな地下水があり、杭列をはじめとする木製品を現代まで保存してきたと考えられます。杭を除く、木製品は20点余りで用途がはっきりしないものもありますが、石斧の柄、浅鉢、片口容器、丸木船の櫂?、堀棒などが出土しています。まだこれらは調査中ですが、今回はその一部を紹介してみましょう。
写真は石斧の柄、浅鉢、堀棒の3点です。これらはハルニレ、クワ、ナラの木が使われています。詳しく観察しますとその制作には、素材の性質を巧みに利用して作られています。


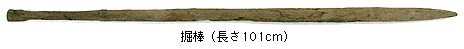
たとえば石斧の柄は図のように枝と幹を利用して、浅鉢は石のナイフなどを利用して側面などは厚さ5ミリ程度まで薄く削られています。しかもこの浅鉢の内面には赤い漆も塗られています。
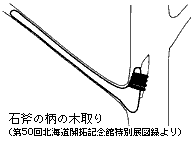
また、堀棒はかの有名な青森県三内丸山遺跡でも出土していますが、具体的な使用法は不明です。北海道の縄文遺跡で木製品が出土したのは49号遺跡も含め、わずかに9遺跡ほどで当時の木製品はまだまだ分かっていません。49号遺跡ではさらに木製品の出土が予想されていますので、今後の調査が期待されています。
なお、紅葉山49号遺跡の発掘調査は10月まで続けられていますので一度見学においで下さい。(石橋孝夫)
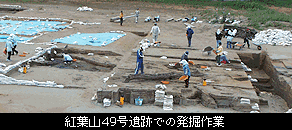
(※この文章は「広報いしかり」平成13年8月号に掲載されたものです。)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











