2006年
石狩レポート#057(2006年12月20日)

親船名無沼も、全面結氷しています。
あれだけたくさんいたカエルやドジョウも、土の中や氷の下で、春を待っているのでしょう。
夏の画像(石狩レポート#047)とくらべてみてください。
石狩レポート#056(2006年11月25日)

資料館の隣では、旧長野商店の復元工事が進行中。
明治20年ごろ、この町に建てられた歴史的建造物ですが、道路の拡幅のため、資料館の隣に移転することになりました。
2007年4月からの公開を目指し、日没後も作業が続きます。
石狩レポート#055(2006年11月11日)

貝殻をつくるタコ、カイダコ(アオイガイ)を解剖。
執刀するのは、北大の山本さんです。
取り出した臓器は液浸標本にして、胃は内容物(食べている物)を調べる予定です。
「お願い」
資料館では、研究のためにアオイガイ漂着情報を集約しています。
採集した方は、日時・場所・サイズなどの情報を教えてください。
生態の解明、海洋環境の調査のため、ご協力お願いします!
石狩レポート#054(2006年10月22日)

これがアオイガイの中身、カイダコです!
一見ふつうのタコのようですが、腕(いわゆる 足)に注目。
1対の腕が扇状に平たくなっています。
これが、あの繊細で美しい殻を作る「道具」なのです。
「お願い」
資料館では、研究のためにアオイガイ漂着情報を集約しています。
採集した方は、日時・場所・サイズなどの情報を教えてください。
生態の解明、海洋環境の調査のため、ご協力お願いします!
石狩レポート#053(2006年10月15日)

ついに生カイダコ(アオイガイ)確保!!!
しかし、すぐに死んでしまいました。
写真は冷凍保存中のものです。
これらは資料館の標本として、調査研究に活用します。
「お願い」
資料館では、研究のためにアオイガイ漂着情報を集約しています。
採集した方は、日時・場所・サイズなどの情報を教えてください。
生態の解明、海洋環境の調査のため、ご協力お願いします!
石狩レポート#052(2006年10月5日)

石狩浜で今年初のアオイガイの漂着を確認!
アオイガイはカイダコとも呼ばれるタコが作る貝殻。
本来は熱帯から温帯の暖かい海に棲息するのですが、海流に流され、はるばる北海道までやってきました。
「お願い」
資料館では、アオイガイ漂着情報を集約しています。
採集した方は、日時・場所・サイズなどの情報を教えてください。
生態・海洋環境の調査のため、ご協力お願いします!
石狩レポート#051(2006年9月29日)

アキアカネの群れが産卵しています。
駐車場の水たまり、砂浜など、水気のあるいたるところに産み付けています。
そんなところではすぐに干上がってしまうのに。
石狩レポート#050(2006年9月8日)

モクズガニに、びっしりフジツボ。
これは浜に漂着していた死骸ですが、死骸の新鮮さ、フジツボの大きさから、生きていたときからこんな状態だったようです。
なんだか貫禄を感じさせます。
石狩レポート#049(2006年8月26日)

浜でコハクを拾いました。
直径1cm足らずの小さなものですが、きれいな赤色をしています。
コハクは樹脂の化石なので、石炭と一緒に石狩川の上流から流れてくるのでしょう。
石狩レポート#048(2006年8月6日)

石狩浜の親船名無沼。
この季節、たくさんのヒツジグサの花が見られます。
未(ひつじ)の刻(午後1時から3時)に花が開きます。
石狩レポート#047(2006年7月20日)

石狩浜の名も無き沼にも、夏がやってきました。
もともとは砂利採取跡の窪地だったのが、数十年の歳月を経て、今では立派な水辺です。
春秋にはカモが羽を休め、夏にはトンボが飛び交い、たくさんのヒツジグサの花も見られます。
石狩レポート#046(2006年6月27日)

鷲岩。浜益区の愛冠岬です。
巨大なワシが立っているように見えます。
浜益の海岸線は新第三紀の火山岩からできていて、知床や積丹に負けないくらい、多くの「奇岩」が存在します。
石狩レポート#045(2006年6月18日)
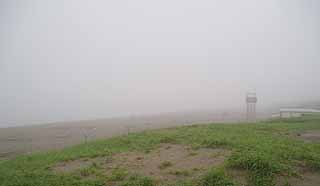
今日の石狩浜は、朝から珍しく濃い霧につつまれました。
いつもなら向こうには海と、増毛山地が見えるのですが。
海からの湿った空気が入り込み、風がほとんどないために、午後になっても霧は晴れませんでした。
石狩レポート#044(2006年6月9日)

地層から突き出した「恐竜のタマゴ」?!
石狩市の厚田から望来の海岸では、およそ800万年前の地層の中に大きく丸い、とても硬い岩石の塊、「ノジュール」が見られます。
その中でも写真は特に大きい物で、直径は4メートル近くあります。
崩れやすいため、今にも落ちて来そうで、とてもコワイです。
石狩レポート#043(2006年5月25日)

厚田区の海岸段丘上から見た、石狩湾岸。
海岸沿いの石狩砂丘(黄緑色の草原部分)は小樽市の銭函から始まり、ここ無煙浜で終わっています。砂丘の総延長は20kmを越えます。
画面上端は手稲の山々で、そのすぐ下に石狩川河口が見えます。
石狩レポート#042(2006年5月11日)

石狩湾に沈む直前の太陽。
真ん丸いはずの太陽が、上下につぶれています。
これは、太陽の上端から来る光と下端から来る光とで屈折の度合いが違うために見られる現象です。
下端からの光のほうが、より厚い大気を通ってくるのが原因です。
石狩レポート#041(2006年4月28日)

目の前の海で、海水と河川水が戦っています!
画面右にある石狩川河口からの濁った雪解け水と、小樽側(画面左奥)からの青く澄んだ海水。
異なった水塊の境界「潮目」には、浮遊物が集まります。
境界がかすかに白く見えているのがわかりますか?
石狩レポート#040(2006年4月14日)

三線浜(石狩湾新港の東側)に、ブンブクの殻が大量に漂着しています。
ブンブクとはウニの仲間で、ここで見られるのはオカメブンブクという種。
普通の放射状のウニを「正形ウニ」というのに対し、こちらは体に前後方向があり、「不正形ウニ」と呼ばれています。
生きている時は、短い棘がたくさん生えていて、浅い海底の砂の中にもぐって生活しています。
石狩レポート#039(2006年4月1日)

海水が石狩川の雪解け水で濁っています。
ここしばらく北からの強い風が続いたため、河口から石狩湾に流れ出た水が吹き寄せられているのです。
この日の塩分濃度は1.3%、平均値の3分の1近くまで真水によって薄められていました。
川のにおい(ドブのようなにおい)もします。
石狩レポート#038(2006年3月24日)

石狩浜の西部(小樽市)に、トドの死体が漂着していました。
体長3.2mのオスです。体重はおそらく1tくらいあるでしょう。
まだ腐敗しておらず、鳥にもほとんど食われていない状態です。
2から3日前の荒天時に打ち上げられたものと思われます。
石狩レポート#037(2006年3月10日)

石狩川河口で見つけた水鳥(ウミアイサ?)の死骸。
首から胸にかけて、黄色い釣糸が絡みついています。
石狩レポート#036(2006年3月5日)

今シーズン初の「砂茶碗」を見つけました。
ツメタガイという巻貝は、砂を固めてその中に卵を産みつけます。
それが砂茶碗。春先の海岸でよく見られます。
もっと大きいものになると、くるっと巻いて、本当に茶碗のような形になります。
石狩レポート#035(2006年2月11日)

地吹雪の続く、石狩川河口そばの本町地区。
それでもたまに訪れる晴れ間には、積雪と地吹雪による見事な造形も見られます。
石狩砂丘にて。
石狩レポート#034(2006年1月29日)

茨戸川の魚といえば、ワカサギ。
茨戸川と石狩放水路の分岐点(川の博物館そば)は、ワカサギ釣りで賑わっています。
ウグイもけっこう釣れているようです。
石狩レポート#033(2006年1月26日)

石狩川も凍りました。
1972年まで河口付近には川を渡る橋はなく、夏は渡船、冬は川の氷を柳の枝などで固めて氷橋として、対岸まで歩いて渡ったそうです。
石狩レポート#032(2006年1月9日)

遠くに巨大な黒い物体が見えたので近寄ってみると、浮きの一種でしょうか。長さ3から4m。木製のようです。
港か大型船か何かで使っていたもの?
13日に行ってみたときには、もう消えていました。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











