いしかり博物誌/第23回
第23回 手稲山が生んだ? 紅葉山砂丘

札幌市の手稲前田から石狩市の花川、生振(おやふる)、美登位(びとい)(びとい)へと続く細長い砂の丘が、紅葉山(もみじやま)砂丘です(写真1)。すでに大半が失われ、今では断片的に残っているだけですが、今からおよそ6000年前は、当時の海岸から伸びる2本の細長い砂州(さす)でした(図1)。その後、海水面の低下によって陸地になり、さらに風によって砂が吹き集められてできたのが現在の砂丘です。
現在、砂丘がよく残っているあたりを歩いてみると、丸い、こぶし大の小石が地面に転がっているのを見ることがあります。実はその丸い石は、地下で砂丘に沿ってびっしりと集まっていて、紅葉山砂丘の土台となっているものです。この石はどこにでもある石のようですが、砂丘誕生の秘密を解く手がかりがここに隠されています。
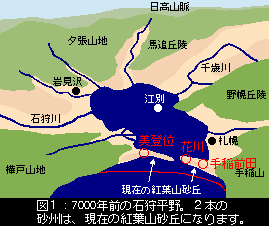
まず石の形。丸いといっても、場所によって微妙に違いがあります。手稲前田で見られる石はボールのように球状をしていて、大きさはまちまちです(写真2)。このような特徴は河原の石によく見られます。それに対して花川で採れた石は、碁石のように平べったい円盤状で、大きさはだいたい揃っています(写真3)。これは海岸の石の特徴です。つまり、石は山の方から川の流れによって、当時の海岸まで運ばれてきた、ということがわかります。
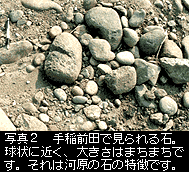
もうひとつの手がかりは石の種類です。手稲前田や花川の石は、ほとんどが溶岩が冷えて固まってできた火山岩でできています。これは手稲山周辺の山々を形作っている岩石です。ところが美登位(びとい)で採れた石は、多くが砂や泥でできた堆積岩でした。こちらは石狩市北東の樺戸(かばと)山地を作っている岩石です。
どうやら砂丘の土台の石たちは、花川より西では手稲山が、美登位(びとい)より東では樺戸山地が、川によって削られ、海まで流されてきた石が集まったものだったようです。
紅葉山砂丘は手稲山と樺戸山地の子ども、ということでしょうか。(志賀健司)
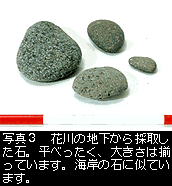
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











