いしかり博物誌/第25回
第25回 風と砂に育まれた砂浜のトップランナー
夏、石狩浜でキャンプや海水浴を楽しむみなさんの目に映った植物、それは美しい花々というよりは、飾り気なく緑の葉を茂らす雑草と呼んでしまうような植物だったのではないでしょうか。私たちの目は、色鮮やかな花をつける植物に向きがちですが、今回は、石狩浜で海に最も近い所に繁茂する植物について紹介します。
砂浜でみなさんが目にする雑草とも呼べるような植物、それは「ハマニンニク」で、イネ科の植物です。名前にニンニクとついていますが、単に葉が似ているためであって、食べるニンニク(ユリ科)とは全く別ものです。
別名「テンキグサ」と言い(「テンキ」はアイヌ語で籐(とう))、アイヌの人たちはこの葉で籠(かご)を編んだと言われています。
このハマニンニクは、石狩浜の中でも、海からの風がよく当たり、砂がよく積もる場所に多く育っています。この場所は、みなさんが海水浴を楽しむ砂浜のすぐ背後に当たります。
一方、おなじみのハマナスは、砂の移動が激しい場所ではあまり育つことができず、砂地が安定している場所に育ちます。石狩灯台周辺でハマナスの群生が見られるのは、ここの砂地が安定しているからです。


砂の中のハマニンニクを見てみましょう(図)。砂中に埋もれていて根のように見える部分が実は茎です。砂が積もるたびに、地上に葉を出すため埋もれた茎が上へあるいは横へ伸びた結果です。この茎は深い所で地中2メートルほどまで続き、次々と積もる砂の上に必死に茎を伸ばしていったことがわかります。
もちろん根もあります。茎の節目から出る細いヒゲのようなものが根です。
こういった茎の伸ばし方ができるからこそ、他の植物が育つことができない、砂が次々と積もる環境に育つことができるのです。逆に砂地が安定してくると、ハマナスやススキなど他の植物たちが勢いを増し、植物同士の競争に弱いハマニンニクは次第に少なくなっていきます。
風が運ぶ砂を味方につけて砂丘の最前線で繁栄するハマニンニク。この飾り気がなくてもたくましい植物に、厳しい環境に巧みに適応した植物の知恵を垣間見ることができますね。(石狩浜海浜植物保護センター/前野華子)
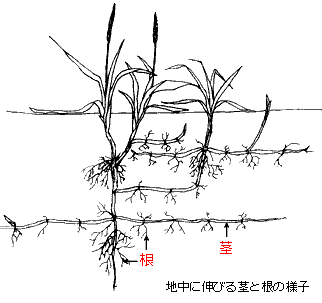
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











