泥炭
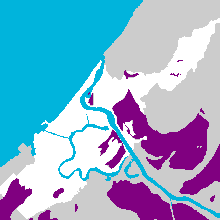
(垣見,1958を改変)
泥炭、泥炭地とは
温帯北部の湿地のように水分が多く、気温の低いところでは、ヨシ、ハンノキ、スゲなど植物遺体は、微生物の働きが不活発なために埋もれた植物質の分解が不十分で、スポンジ状・繊維状の褐色の土塊となりますが、これを泥炭、ピート、あるいは草炭と云います。泥炭は、日本では1年に0.5から1.5ミリメートルほど堆積しますが、地下水位より低いか同じ位置で作られる低位泥炭(ヨシ、ハンノキなどの遺体が主)、地下水位より高い位置で作られる高位泥炭(ミズゴケなど)、その中間の中間泥炭(ワタスゲなど)に分けられます。
その用途は、保水材、培養土、土壌改良材、建築資材、ウイスキー製造の麦芽乾燥、燻蒸材等に使われる他、かっては燃料としても使用されていました。
泥炭が排水後も厚さ20センチメートル以上覆っている土地のことを泥炭地と云います。
北海道の泥炭地の総面積は、約20万ヘクタールで、本州では高山地の湿原(尾瀬ヶ原など)に局地的にしかみられず、平地では下北半島に小規模に分布するものが南限です。泥炭地は、強酸性で無機成分に乏しく、夏季高温時には分解が進んで窒素過多になりやすいなど、もともとは農業に向かない土地ですが、排水や客土などの改良が行われて現在では多くが農地となっています。
石狩の泥炭
旧石狩市では泥炭は、薪材が乏しくなった大正時代に燃料として使われるようになりました。スコップやスペートと呼ばれる専用のスコップなどで掘り取った泥炭を風が通るように積み上げて秋まで乾燥させ冬に泥炭ストーブで燃やしました。また、生振(おやふる)の泥炭は良質であったため、ニッカウヰスキー余市工場の原料麦芽の乾燥用、燻蒸用として使われました(現在では、余市工場の体験教室でのみ使用されてます)。
第二次世界大戦前後には、石炭の不足で泥炭が主な燃料として使用されましたが、その後石炭が、さらに石油が安価になって、昭和30年代後半になると燃料として使用されることはなくなりました。
(石井滋朗)
参考文献
- 貝塚爽平・成瀬洋・太田陽子・小池一之(1995)日本の平野と海岸.岩波書店.
- 垣見俊弘(1958)5万分1地質図幅「石狩」.地質調査所.
- 株式会社クボタ広告宣伝部(1976)アーバンクボタ(13).株式会社クボタ.
- 株式会社クボタ広告宣伝部(1985)アーバンクボタ(24).株式会社キボタ.
- 下中直人(1988)世界大百科事典.平凡社.
- 鈴木トミエ(1996)石狩百話.石狩市.
- 渡辺喜久雄(1981)北海道大百科事典下巻.北海道新聞社.
- 山地肇治(1992)生振開村百二十年.生振開村百二十年記念事業協賛会.
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会社会教育部 文化財課
〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館
電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











